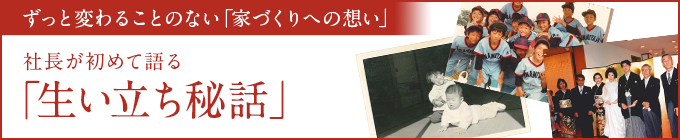「許容応力度計算」って何のこと?
許容応力度計算とは、建築基準法に定められた構造計算手法の一つで、地震や風などの力がかかったときに、建物の各構造部材がその力に耐えられる限界値(許容応力度)を上回るように計算する方法です。
これは、基礎、梁、柱、接合部など、構造部材の全てを複雑な構造計算ソフトを用いて立体的に確認する、最も信頼性の高い計算方法と言えます。
2025年4月から、これまで多くの2階建てや平屋の木造住宅に適用されてきた「四号特例」(構造計算書の提出省略)が変更され、多くの住宅で構造関連図書の提出が必要になりました。ただし、許容応力度計算そのものが全ての住宅で義務化されたわけではありません。
同じ「耐震等級3」でも、計算方法でこんなに違う!
建物の耐震性を示す「耐震等級」は1~3があり、耐震等級1が最低基準、耐震等級3が最も強いとされます。耐震等級3は、建築基準法レベルである耐震等級1の1.5倍の地震力に対する強さを持つとされています。
しかし、「耐震等級3」という表示であっても、どのような計算方法で算出されたかによって、実際の強度が大きく異なることをご存じでしょうか。耐震性を測る主な方法は以下の3つです。
1.仕様規定の計算
最も簡易的で、耐力壁の量や配置バランスなどを確認するのみ。詳細な応力計算は行われず、耐震等級1しか取得できません。
2.品確法の計算(性能表示計算)
長期優良住宅の基準にもなり、仕様規定より詳細な計算を行いますが、梁や基礎の設計は簡易的な表を用いる場合があります。耐震等級2や3も取得可能です。
3.許容応力度計算(構造計算)
最も高度で安全な計算方法です。基礎や構造材、接合部の強度までを総合的かつ精密に算出します。
同じ「耐震等級3」であっても、品確法の性能表示計算で算出された場合の強度ランクが1.9から2.0なのに対し、許容応力度計算では2.4から2.7と、大きく異なることがあります。
これは、許容応力度計算では耐力壁の壁倍率の上限が7倍まで認められるなど、より高い強度の設計が可能になるためです(品確法では5倍が上限)。
また、「耐震等級3相当」は認定機関の審査を受けていないため、その耐震性が確認できないことに注意が必要です。
コストは「安心への投資」
許容応力度計算は、最も詳細な計算を行うため、設計コストや時間、手間がかかります。そして構造材の強化などで工事費用がプラスになることもあります。
しかし、これらの費用は単なる「支出」ではありません。地震による建物の倒壊や大規模な損傷が発生した場合の費用は、この比ではなく、「安心への先行投資」と捉えるべきです。
まとめ
安全・安心な家とは、「地震に対して命を守る家、そしてその後も住み続けられる家」です。
長期的な安心安全を考えると、許容応力度計算は、迷わずやるべきことだと私たちは考えます。
家づくりは一生に一度の大きな買い物です。
目先の費用だけでなく、「この家で何十年も暮らし続ける」ことを想像しながら、家族の命と財産を守る賢い選択をしていきましょう。
このコラムを読んだ方へのオススメ記事

人気のコラム
この記事が気に入ったら
いいね!しよう